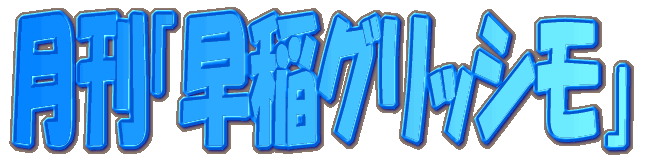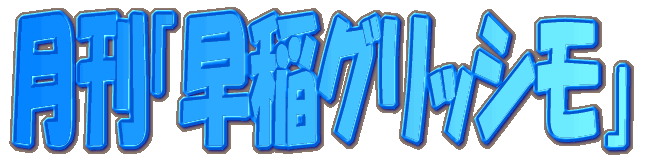|
四連を終えて① |
|
 |
|
「四連を終えて」
第九十九代学生指揮者 市川 真樹
|
|
「ワセグリにしか表現できないサウンド」というテーマを掲げた今年のワセグリ。その前期の集大成の場ともいえる演奏会が四連だった。「四連で今年最高の演奏をする」、代が変わった時から四連を目標に練習をしてきた。送別も六連も、ある意味においては四連へのステップレースだった。「本気で勝ちに行く」ベースパトリの長谷川が言った。
ワセグリが本気で臨む四連。その演奏会において、山田和樹先生に指揮をお願いしたのは必然だった。僕達の想いに真剣に答えてくれる・本気でぶつかってきてくれる・ワセグリにしか出せないサウンドを引き出してくれる、そんな先生だと思う。そして何よりも、「ヤマカズ先生と創る音楽」がやりたくてたまらなかった。
緊張と不安と期待の中で向かえる初のヤマカズ先生練。ワセグリには「先生練習は戦いだ」という言葉がある。真剣勝負の場だ。先生の一言で劇的に変化し続ける音楽。次々と生まれ変わって行く音。真剣さの中に、楽しさや喜びがあった。回を重ねていくごとに、今回の『季節へのまなざし』のカタチがみえてきた。その瞬間に立ち会える幸せ…
そして向かえた四連@京都コンサートホール。素敵なホールだ。
エール交歓が始まる。適度な興奮と緊張感で臨めたと思う。京都のお客様の温かい拍手が嬉しかった。いい演奏会になりそうな予感。
本番直前にヤマカズ先生による練習と気合注入。
そしてワセグリ単独ステージ、『季節へのまなざし』が始まる。
みんなのひたむきな想いが一つの結晶になった。
ずっと探していた「ワセグリの音」にようやく出会えた気がした。
ワセグリには様々な人間がいて、合う人合わない人がいる中で、時には衝突がありつつも、しかしそれでも演奏会という目標に向かってバラバラな個が一つになっていく。それは、とても尊いものだと思う。
みんなが一つになったその瞬間、僕達は本物の「ワセグリ」になれるんじゃないかな。

『早稲田大学校歌』の一節に
集まり散じて 人は変われど
仰ぐは同じき 理想の光
という部分がある。時代の流れと共にワセグリも変わっていく。だけど、そのなかにあっても、受け継いでいきたいと思うワセグリの「魂」があの瞬間、確かに存在した。
演奏が終わった瞬間、今までの出来事が一瞬のうちに頭を駆け巡り、込み上げてくるものが抑えきれなかった。生きていて本当によかった。
最後にグリーメンへ。
ありがとう。みんな最高だった。 |
|
 |
|
「四連・早慶交歓を終えて」
東西四大学合唱連盟理事 倭拓也
第55回6大学定期演奏会 
四連が終わってから1月が過ぎました。
大変多くのお客様のご来場誠に有難うございました。
遠い京都の地のお客様方に暖かく迎えていただきとてもうれしい限りでした。
僕達4年生からしてみれば、最後の四連でしたが自分のできる限りのことができたので満足です。
さてたった3時間の演奏会のために多くの時間をかけられるのはやはり学生の特権でしょうか。
社会人になってからではこれだけの時間を合唱等の趣味にかけられることはないと思います。
今しかできないことを残り少ない時間、一時一時を大事にし最後の定期演奏会に向けてより一層頑張って行きたいと思います。
最後に気にかかるのは四連の人数の減少です。
今回は早稲田が一番多かったとは言っても60人いませんでした。
年々オンステ人数が減っているように感じますが来年の早稲グリ100周年で巻き返しを図り次回の四連には個人的には合同150人のオンステを期待しております。
|
|
 |
|
「ぼろ泣き野郎99の想い」
セカンド4年 外政 中根浩貴
「定演は長丁場で声が荒れる、ほぼ初心者の1年も入ってくる、だから四連でこの代の最高の演奏をする。」
「四連は、ヤマカズ×きせまなで。」
ヤマカズこと山田和樹先生は、過去1年、2年の定演4ステでお世話になってきました。
ヤマカズほどワセグリから“ナニカ”を引き出す指揮者はいないと思っています。
きせまなこと「季節へのまなざし」は荻久保和明氏の作品です。
荻久保作品ほどワセグリ“らしさ”が出る曲はないと思っています。
これが僕らの代の、本気とわがままでした。
きせまなは、
Ⅰ.ひらく Ⅱ.のびる Ⅲ.みのる Ⅳ.ゆめみる
の4楽章から成り、それぞれ順番に春夏秋冬に対応しています。
また、この曲の核とも言えるべきメロディーラインがⅠとⅣに出てきます。
ヴォーカリーズのみで表され、多少の違いがあれど、最後はG♭durに終止する。
冬に春の足音が聞こえるような、そんな季節の巡りを思わせるのです。
早慶交歓演奏会を前にした6月13日、指揮者の岩城宏之氏が亡くなられました。
その日の夕方練習がちょうどあり、ヤマカズはやはり少々落ち込んでおられました。
Ⅳの、上に説明した部分の練習中、僕にとって、最も重要となる指示が出されました。
「ここはⅠとは変えてくれ。」
「Ⅰではまだ単なる春の喜びでいい。」
「しかしⅣのここは違う、恋人でも誰でもいい、誰かを想って歌いなさい。」
「僕も、ここは岩城先生を想って振るから。」
誰かを想って、歌う。
僕はすぐに、今年の冬に亡くなった、おばぁちゃんを頭に浮かべました。
僕は愛知の片田舎出身です。
おばぁちゃんは、僕が高3の夏に脳梗塞で倒れ、手術後左半身まひとなってしまいました。
でも、意識だけは、ほんとずっとしっかりしていて。
だから余計に、どれだけ、そんな自分の姿が悔しかったことか。
うちは両親がともに教師で、家で介護できる状態ではなく、おばぁちゃんはずっと入院生活で、たまのイベントに家に数時間戻るだけでした。
おばぁちゃんは、亡くなる前日に、いろいろなことを書き残していました。
もどかしい。いえにかえりたい。
ひろきけんこうなうちにもどってくるよう。
はやくかえりたい。
ろくに実家に帰らんかった自分が、とても悔しい。
大学受かったとき、寂しさ隠し喜んでくれたのに。
お見舞いに行けば、泣いて喜んでくれたのに。
握手をすれば、びっくりするくらいの力で握り返してくれたのに。
病室から出たあとでも、手を振り続けていてくれたのに。
髪を染めて帰れば、都会の色だ、と言ってくれたのに。
いつ帰ってくる、と必ず聞いてくれたのに。
大切なことは、なくして初めて気がつく、にも、ほどがある。
“みえないことでみえてくる世界”
“みえてくるしあわせ、みえてくるふしあわせ”
Ⅳの詞が、おばぁちゃんのこととして、僕に沁みるのでした。
四連、当日。
本番直前まで、ヤマカズは控え室での最後の確認に付き合ってくれました。
アーティストラウンジでの待機中、学指揮の話に涙する後輩にもらい涙をしました。
これ以上ない、満たされた気持ちでステージにあがることができました。
春、夏と冷静なふりをして歌い。
秋に昂ぶりすこし涙を我慢し。
ついに、最後の冬になりました。
練習番号3。
“みえないことで、ルルル…”
感謝と後悔で、おばぁちゃんを想います。
一度も生でワセグリを聴かせられなかった、おばぁちゃんの顔が客席に浮かびます。
ヴォーカリーズに入ってすぐ、ぼろっぼろと涙がこぼれました。
練習でも、早慶交歓でも涙ぐむくらいだったのに。
その最後のG♭durはあまりの声の震えから歌えませんでした。
途中で泣いてしまうなんて、歌い手としては失格なのかもしれません。
子音を出しすぎたり、体を揺らしすぎたり、叫びすぎたり、音楽とは言えないかもしれません。
でも、それがワセグリで、それでいいんだと、今回思いました。
こんなにものめり込み、気持ちを乗せて歌えることなんて、滅多に出来ないことです。
音がどーたら、言葉がこーたら。
そんなことを、1段抜かしで飛び越えてしまえたぐらいの“うた”が歌えたことを誇りに、幸せに思います。
その陰には、恵まれた環境と、今がありました。
共に声を出してくれるワセグリの仲間。
この前お引越しをお手伝いしたヤマカズ。
至らない僕を支えてくれた友人、家族。
早慶交歓、四連を聴きに来てくださった方々。
そして、こんな文章をここまで読んでくださった皆様。
いくら感謝してもしきれません。
しきれないよ。しかたがないから、カウボーイにでもなろうかな(笑)
おばぁちゃんの100日で実家に帰ったとき、お坊さんがおっしゃいました。
「100日とは、泣くのをやめる日である。」
また、Ⅳの最後はこう結ばれています。
“雪の白さが悲哀(かなしみ)を讃歌(ほめうた)に変えるまで”
僕にとっては、四連こそが、“100日”だったのかもしれません。 |
|
 |
|
「四連を終えて」
トップ四年 南遼
早慶交歓で、喉を潰した。
私の喉は滅多なことでは音を上げないと思い込んでいた。
演奏会で喉を嗄らした記憶は、新入生時の初舞台である「金の卵コンサート」まで遡らなければならない。
「季節へのまなざし」は没入しやすい曲である。
そのため、ひとつまみの冷静さを保とうという意識をもっていた。
にもかかわらず、このような不可解な事態が起こった。
このことに象徴されるように、四連の期間は、論理的には割り切れない何とも言えない情動に突き動かされ続けた時間であったな、と1ヵ月経った今、勝手に感じている。
日常会話にも支障が出るほどの喉の嗄れは、四連単独ゲネプロで完全に復調するまで続いた。
四連単独本番では、自分も含めた団員が、何かに取り付かれていたように感じた。
「憑依」という言葉がまさしく当てはまる。
経験上、本番は興奮と緊張であっという間に時間が流れるものである。
それが、妙に眼前の時間がゆったりと流れるのである。
没入しているのに、部分部分を意識的に歌えるのである。
山田和樹先生と四連の期間を過ごせたこと、そこで得たことを、私が文字に起こそうとすると、現実に起こったことに比べて陳腐になってしまうので、何とも書き表せない。
しかし、20代の山田和樹先生と「季節へのまなざし」を真剣勝負で対峙し、ステージに立てたことが何よりの幸せであったということは確実に言える。
四連は、得てして箱根の山を越えようとしない、ものぐさな関東人にとって、外の風にあたれる絶好の機会である。
音楽は芸術性の追求とポピュラーな広まりの両立というのは難しい。
しかし、四連はそれを実現出来る場であると思う。
私はこれまで実務面でそのことに貢献出来たとは言えない。
しかし、芸術性とポピュラーな広まりの間の架橋という四連の「魂」を、日々の姿勢で次代に伝えていくのが、卒団までに自らがすべきことであると感じている。
ご来場の皆様、ご指導いただいた先生方、ご支援いただいた方々、さらに、四連の他の三大学の皆様に御礼申し上げます。
|
|
|
|
|
|
|